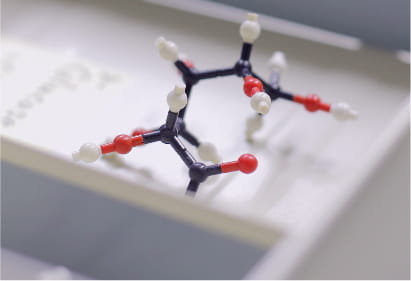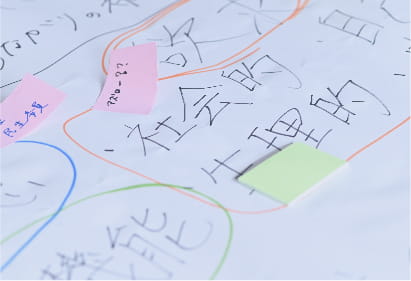人と向き合う、
確かな信頼を得るために
保健福祉学部は、看護学科と栄養学科の他、2021年4月に誕生した現代福祉学科と子ども学科の4つの学科から構成されています。 保健福祉学部では、看護、栄養、福祉、幼児教育(保育)の分野で、地域社会や国際社会の人々の健康維持と増進に積極的に貢献できる人材の育成を目指しています。
保健福祉学部は、看護学科と栄養学科の他、2021年4月に誕生した現代福祉学科と子ども学科の4つの学科から構成されています。 保健福祉学部では、看護、栄養、福祉、幼児教育(保育)の分野で、地域社会や国際社会の人々の健康維持と増進に積極的に貢献できる人材の育成を目指しています。
岡山県立大学保健福祉学部では、少子高齢化やグローバル化が進む社会において、看護学、栄養学、社会福祉学、幼児教育学の分野から、人々の健康や幸福のために貢献できる人材を育成しています。
保健福祉学部では、不確実性の高い現代社会において、人々が幸福に暮らせるための未来像を描き、その未来像を実現させるための豊かな人間性、理論的知識、実践力、そして、他者と協働する力を育成します。
そのために、吉備の杜のプロジェクトを含む、地域における様々な専門的活動プログラムや、海外の大学との学術・文化交流プログラムを積極的に実施しています。
瀬戸内海に近く、緑豊かな古代文化の地にある岡山県立大学で、皆様とお会いできることを楽しみにしております。
保健福祉学部長 近藤 理恵
自主性と豊かな人間性を育み、
全人的ケアのできる看護のプロヘ。

食と健康の相互関係を科学し、
健康づくりに貢献する専門家へ。

知ってください!
あなたを必要な人がいます。

子どもとともに、
地域とともに未来を育む。